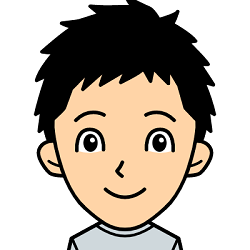
社会的手抜き、リンゲルマン効果とは?
社会的抑制との違いとは?
社会的手抜きの例と対策を知りたい!
そんなあなたへの記事です。
集団で何かを作業するとき、ついさぼってしまったことはありませんか?
職場で手を抜いている人はいませんか?
今回は社会的手抜きについて解説します。原因については特にくわしく解説しますので、社会的手抜きへの対策がわかるようになります。
やや長いですが、具体例を交えながら簡潔に説明していきますので、6~7分ほどお付き合いください。
✔本記事のテーマ
【社会的手抜き?】リンゲルマン効果の例と対策をわかりやすく解説
✔本記事でわかること
- 社会的手抜きとは?
【意味/関連実験/具体例・原因・対策】
社会的手抜きとは?
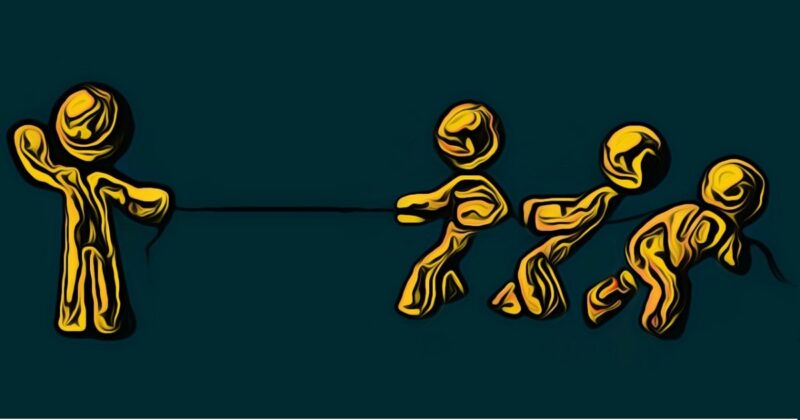
1.社会的手抜きの意味
周囲に自分以外の人がいることで、パフォーマンスが高くなることを社会的促進、パフォーマンスが低くなることを社会的抑制といいます。
社会的手抜きは社会的抑制の一種で、他者に頼ることができる状況下で発生する心理現象です。
個人が集団内で作業を行うときに、他の人が取り組んでくれることを期待して手を抜いてしまう傾向を指します。つまり、自分自身の能力を集団内で十分に発揮することができなくなる特性があります。
社会的手抜きには様々な別名があります。一般的な呼び方としては、「リンゲルマン効果」「社会的怠惰」「フリーライダー(タダ乗り)現象」といった言葉が使われます。
2.関連実験
社会的手抜きに関連する、リンゲルマンの実験、ラタネとハーディーの実験、ザッカーロの実験を見ていきましょう。
①リンゲルマンの実験
社会的手抜きの研究において、マックス・リンゲルマンというフランスの農学者が行った実験があります。
- 被験者に綱引きや荷車を引くという力仕事を行わせ、参加人数に対する1人当たりのパフォーマンスを数値化した。
- 実験の結果、1人が綱引きや荷車を引くのに用いる力を100%とした場合、2人の場合は93%、3人の場合は85%…と低下していき、8人の場合には49%まで低下した。
これにより、集団で作業を行った場合、1人当たりの作業量が低下していることが示されました。
②ラタネとハーディーの実験
ラタネとハーディーが行った実験について説明します。
- ついたてをはさんで2人のチアリーダーを座らせた。
- アイマスクとヘッドホンを着けさせ、お互いの行動が分からない状態にした。
- 単独の条件とペアの条件のそれぞれで大声を出させ、音量を計測した。
- ペアの条件での音量は単独のときと比べて音量が94%しかなかった。
- 被験者はどちらの条件でも全力で大声を出していたと思っていた。
結果、被験者は無意識に手抜きをしてしまったということです。
このことから、リンゲルマン効果は「社会的手抜き」と呼ばれるようになりました。
ラタネとハーディーといえば、傍観者効果の実験者として有名です。
ニューヨークで起きたキティ・ジェノヴィーズ事件において、目撃者が38名いたにも関わらず、誰一人通報をしようとせず、誰一人被害者を救出しようとしないということが起こりました。
この事件をもとにラタネとハーディーは傍観者効果を提唱しました。集団心理により行動が抑制されるといった点は、社会的手抜きと共通します。
参考記事を載せましたので、よろしければそちらもご覧ください。
③ザッカーロの実験
最後にザッカーロの実験です。
- ある集団の人数が2人から4人になったときの生産性の変化を調べた。
- ある集団には社会的に有意義で、成果に応じて報酬が支払われる課題が与えられた。
- もう一方の集団には普通の課題が与えられた。
- 有意義な課題が与えられた集団は、人数の増加に伴って生産性が上がった。
- 普通の課題が与えられた集団は、人数の増加に伴って生産性が下がった。
この実験により、課題や作業に意義が加わると、社会的手抜きが抑止されることがわかりました。
3.社会手抜きの意外な例
集団で綱引きをしているとき、力を抜いていた。
みんなで合唱しているとき、口パクをしていた。
このようなわかりやすい社会的手抜きの例がある一方で、意外な例があることがわかりました。
それは、公共の場でのマナー違反です。
公共の場では、一人ひとりがマナーを守ることが求められます。しかし、社会的手抜きが起きると、人々は他人に迷惑をかける行動をとることがあります。たとえば、ゴミを散らかす、列に割り込むなどです。
社会的手抜きは集団内で一人当たりの生産性が低下する現象ですが、この場合は一人当たりのマナーが低下したということです。
4.社会的手抜きの原因
次に、社会的手抜きの原因を見ていきましょう。原因を知ることで、対策方法がわかります。
①評価や報酬、集団への不満
集団の中で自分だけが評価される可能性が低い場合、社会的手抜きが起こりやすくなります。
自分の努力が集団に埋没してしまうため、努力をしなくなってしまいます。
このあたりは学習性無力感と共通点がありますね。
学習性無力感とは、自分たちの行動が結果に影響を与えないと感じたときに、無力感を覚え、その行動をあきらめてしまう現象です。
また、自分より優秀な人がいる集団、あるいは、自分だけが優秀な集団でも社会的手抜きは起こりやすくなります。
優秀な集団では自分の努力が生産性にほぼ影響がないため、努力をしなくなってしまいます。
逆に低調な集団では、自分が努力をするのが馬鹿らしく感じてしまうかもしれません。その場合、周囲の低パフォーマンスに同調し、緊張感や注意力が低下してしまいます。
②他者への依存、責任の分散
誰かが何とかしてくれる、このような他者への依存が社会的手抜きの原因になります。また、責任の分散も原因になります。
先ほど紹介したキティ・ジェノヴィーズ事件が典型です。この事件では、「誰かが何とかするだろう」「自分だけが行動する必要はないよな」という認識が悲惨な結果の一因となっています。
③利益優先、モラルの欠如、曖昧なルール
社会的手抜きは、個人の利益や快適さを優先する結果として生じることがあります。個人が自分の利益を最大化しようとする一方で、他人や社会への貢献を軽視することが原因となります。
また、モラルや倫理観の欠如によって引き起こされることがあります。個人が他人への配慮や責任を重視せず、自己中心的な行動をとる傾向がある場合、社会的手抜きが発生しやすくなります。
また、特定集団において社会的手抜きが常態化しているなど、周囲の環境の影響も大きいです。
さらに、ルールが設定されていない場合も社会的手抜きは起きやすくなります。特に手抜きに対する罰則が明確になっていない場合、社会的手抜きが起こりやすくなります。
以下は非倫理的な行動をとる人の心理に焦点を当てた記事です。よろしければご覧ください。
5.社会的手抜きへの対策
社会的手抜きに対する対策は、個人と社会の双方において重要です。以下に、社会的手抜きに対する具体的な対策をいくつか挙げます。
①ルールの明確化と適切な賞罰の設定
倫理的な意識と社会的責任を高めるために、モラル教育が重要です。
ですが、モラル教育が難しいことはご理解いただけると思います。年齢を重ねれば重ねるほど、価値観の変化は望めないので、大人の集団ではより一層難しくなります。
そこで、ルールを明確化することが重要になります。特に賞罰の規定です。社会的手抜きに対しては罰則を強化するのが一般的な対策です。
ただし、賞罰の規定によりモチベーションが低下することがあるので、慎重に設定する必要があります。
②1人ひとりへの声掛け
社会的手抜きは本人が無意識に行っている可能性があります。本人はさぼっているつもりはないということです。
なので、全体に「さぼるなよ~」と言っても、意味がない場合がほとんどです。そこで、個別の声がけが重要になってきます。
また、「自分が努力しても意味がない」と感じてしまわないように、一人ひとりの努力を評価することも重要です。
③意義を見出す
ザッカーロの実験で示された通り、社会的手抜きの抑止には意義を見出すことが重要です。
例えば作業の指示を出す立場であれば、まずは作業の意義をきちんと説明することです。
今回は以上です!



コメント