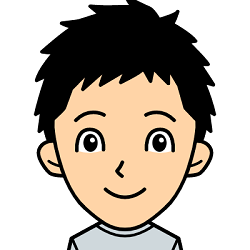
おなら恐怖症とは?
おなら恐怖症あるあるを知りたい!
おなら恐怖症の治し方を知りたい!
そんなあなたに向けた記事です。
おならが怖くて怖くて仕方がない……
中には日常生活に支障をきたすレベルで恐怖する人もいます。
周囲からは理解されない、しかし、本人にとっては極めて深刻なおなら恐怖症について、様々な観点から解説していきます。
さっそく始めます。
✓恐怖症一覧
✓本記事のテーマ
【おなら恐怖症の心理】学校に行きたくない…体操座りが怖い…【治し方も紹介!】
✓本記事でわかること
おなら恐怖症とは/おならに恐怖する原因/過敏性腸症候群・自臭症との関連/おなら恐怖症の治し方など
おなら恐怖症の心理・原因・対処法

1.おなら恐怖症とは?
おなら恐怖症(flatulophobia)とは、公衆の面前でおならをしてしまうことに過剰に恐怖する症状です。
若い女性に多く、人前でおならをしてしまう恐怖から、学校や会社に行きたくないと感じる人もいるそうです。
これには、通学・通勤中におならをしてしまうことに対する恐怖もふくまれます。特にバスや電車、エレベーター内での閉鎖空間などでその恐怖は増長します。
おなら恐怖症の人は自分の家では恐怖が和らぐことが多いのですが、緊張を強いられる人が多い場面であればあるほど、おならをしてしまわないか心配が増していきます。
異性、特に好意を寄せる人が周囲にいる場合は緊張がピークに達してしまいます。
中には社会生活に支障をきたすレベルでおならに恐怖し、引きこもりにまでなってしまう人もいるのだとか。
2.おなら恐怖症の人は何に恐怖している?
おならの音が出ることより、自分のおならが他人に臭いと思われることが嫌な人の方が多いそうです。
「くさッ」て言われたら、それはそれはショックでしょう。
おならが臭いと思われることに恐怖する人は、おならを過剰に我慢するようになります。
また、おならが出ないような状態にも関わらず、「なんだかお腹が痛くなってきた気がする」「おならが出そうな気がする」などと、勝手にマイナスの想像をふくらませてしまうこともあります。
さらにおならを我慢しているとき、ガスが漏れているのではないかと心配になる人もいるそうです。
3.過敏性腸症候群との関連は?
過敏性腸症候群とは、腹痛や便通の変化などの諸症状が同時に現れる胃腸機能障害です。
その中でもガス型と呼ばれるタイプではガスがお腹にたまりやすく、おならが頻繁に出たりガスが自然と漏れ出てしまう場合があります。
そのため、過敏性腸症候群ガス型の人はおなら恐怖症になりやすいといえます。
このタイプのおなら恐怖症の人は、胃腸内科か消化器内科を受診しましょう。
また、過敏性腸症候群はストレスとの関連も強く、神経症や鬱病の一種とみなされることもあります。
ストレスが原因の場合は、心療内科や精神科を受診しましょう。
4.自臭症との関連は?
おなら恐怖症の人は自臭症であることが多いです。おなら恐怖症を自臭症の一つと見なすこともあります。
自臭症の人は口臭や体臭など、自分が発するにおいが他人を不快にしていないか過剰に気にしてしまいます。
本来、誰にでも口臭や体臭はあるものですが、自臭症の人はこれらを過大に解釈してしまうのです。
潔癖で完璧主義な人ほど自臭症になりやすいとされています。
これらの人は、少しのにおいも許せないという思考に陥りがちです。
自臭症は、自分のにおいを客観的に知ることで症状が緩和する場合があります。
例えば口臭チェッカーなどで臭いを数値化することで、「自分のにおいが思ったより臭くない」と理解できます。
5.おなら恐怖症の治し方
おなら恐怖症には誰かに臭いと言われたことがトラウマになって発症するケースがあります。
この場合はカウンセリングなどを通じてトラウマを克服することが必要になってきます。
おなら恐怖症には、実際はおならが臭くないのに思い込みで罹患している場合があります。
この場合は先述の、自分のにおいを客観視することで症状が改善する場合があります。
家族や友人に思い切って相談するようにしましょう。
相談するのは恥ずかしいかもしれませんが、ストレスを抱えたままの状態ではお腹にガスがたまる一方です。
勇気を持って行動しましょう。
また、恐怖症は自分の先入観や思い込みなどの認知の歪みが原因で発症する場合が多いです。
例えば暗所恐怖症では、暗闇に得体の知れないものが潜んでいると思い込んで発症する場合があります。
この場合は暗闇にあえて身を置いて、安全であると正しく認識し直すなど、認知行動療法が症状の緩和に有効です。
ただし、恐怖症を自己判断で治療しようとして逆効果になる場合もあるので、精神科医や心理カウンセラーなどの専門家に頼るようにしましょう。
今回はここまでです。




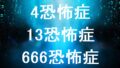

コメント