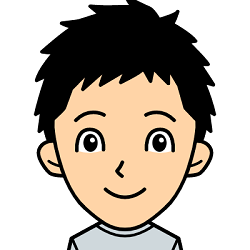
書籍恐怖症とは?
本の何が怖いの?
そんなあなたに向けての記事です。
書籍恐怖症は本に対して恐怖を示す症状です。
本を読むことや理解することに対する恐怖の他に、社会的影響への恐れが含まれる点が、一般的な読書嫌いや本嫌いと異なる部分です。
本記事では書籍恐怖症の解説の他、読書恐怖症、ポエム恐怖症、長い単語恐怖症との関連や克服法について解説します。
※洗脳に関する書籍(Amazonオススメ順)はこちら
✓恐怖症一覧
✓本記事のテーマ
【書籍恐怖症】本が与える社会的影響が怖いという特殊な恐怖症
✓本記事でわかること
書籍恐怖症の3タイプ/克服法:読書や朗読技術の向上・洗脳を解く他
書籍恐怖症の特徴と克服法
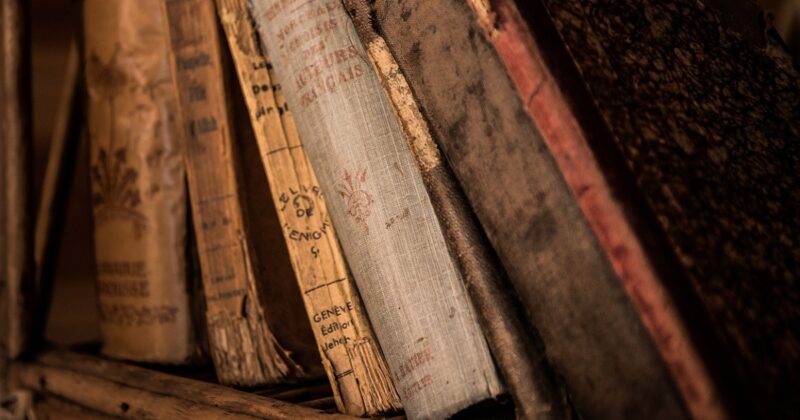
1.書籍恐怖症とは?
書籍恐怖症(Bibliophobia)とは、本に対する恐怖や憎しみが生じる症状です。
書籍恐怖症の恐怖のタイプには様々なものがあります。
①読むことに対する恐怖
このタイプには以下のような恐怖があります。
- 難解な本を理解できないことに対する恐怖
- 人前で音読をすることに対する恐怖
このタイプの恐怖は、ポエム恐怖症や長い単語恐怖症に類するものであると考えられます。
また、「Bibliophobia」を翻訳すると読書恐怖症と表示されることが多いのですが、日本語において読書恐怖症は、何度も本を読み返してしまう強迫性障害の事を指します。
②書いてある内容に対する恐怖
このタイプの恐怖では、特定のジャンルの書籍に対して恐怖します。
特に神話や伝説など壮大な物語に対する恐怖を指す場合が多く、ポエム恐怖症と似ています。
このような壮大なスケールに恐怖する場合は、体が縮こまるような感覚や足がすくむような感覚を覚えることが多いです。
③本が与える社会的影響に恐怖
例えば親が子供に暴力的なコンテンツを見せたくない場合、暴力的な書籍は親にとって恐怖の対象になり得ます。
このように、本が与える影響に恐怖するタイプがあります。
特に宗教に関する本や思想に関する本、自己啓発本などが恐怖の対象となることが多いです。
これらに共通するのは、「洗脳」という言葉と結びつきやすいということです。
このタイプの恐怖の有名な事例として、秦の始皇帝が挙げられます。
中国の初代皇帝である秦の始皇帝は、儒教の思想を恐れて、書物の大量破壊を命じました。
2.書籍恐怖症の克服
①読むことへの恐怖の克服
読むことに対する恐怖の場合は読書の技術や朗読の技術の向上が自信につながり、克服の可能性が高まります。
読書恐怖症、ポエム恐怖症、長い単語恐怖症の記事で紹介した書籍からいくつかオススメを挙げます。
話し方の心構え、知的で合理的な読書の技法、ぶれない思考法の獲得に役立つ内容になっています。
- 頭のいい人が話す前に考えていること(安達裕哉)
- 知的読書の技術(渡部 昇一)
- 実践型クリティカルシンキング(佐々木裕子)
- 「気にしない」練習 ~気持ちを切り替える感情コントロール術~(仏光)
②書いてあることへの恐怖の克服
書いてある内容への恐怖については、曝露療法が有効です。
曝露療法とは、恐怖の対象に自分をさらし、慣れていくという手法です。
ただ、このタイプの恐怖が日常に影響が生じていない場合は特定書籍のみを避けて生活する方が良いかもしれません。
③社会的影響への恐怖の克服
社会的影響への恐怖については、洗脳を解くような手法が必要になってきます。つまり、治療は困難を極めます。
というのも、恐怖症は自身の状態が不合理であることを理解する必要があるのですが、洗脳が生じている場合は不合理であるという考えに至らない場合が多いからです。
恐怖症の治療の前に洗脳状態を解く必要が出てきますので、専門家に頼った方がよいです。一応、洗脳の克服に役立ちそうな書籍を紹介します。
イラストつきでコミカルタッチなので読みやすいです。宗教の二世信者の気持ちが理解できます。
- 洗脳原論(苫米地英人)
恐らく洗脳に関しては日本で最も有名な苫米地さんの書籍。評価が分かれがちな筆者ですが、この本は評価がかなり高めで、科学書の側面もあります。難解な書籍に苦手意識がある場合は同じ筆者作の『洗脳力』がオススメです。
学校で習う常識は害悪であるという論調の本です。ホリエモンの本は総じて読みやすいです。主張に偏りはあるものの、テンポよく読めることができるのでオススメです。
- 洗脳 地獄の12年からの生還(Toshl)
元X_JAPANのToshiによるベストセラー本です。洗脳の巧妙な手口や克服までの道程を体験談をもとに語られています。
一般的な恐怖症の治療方法はこちら
その他の恐怖症は以下の記事よりご確認ください。
今回はここまでです。
※洗脳に関する書籍(Amazonオススメ順)はこちら
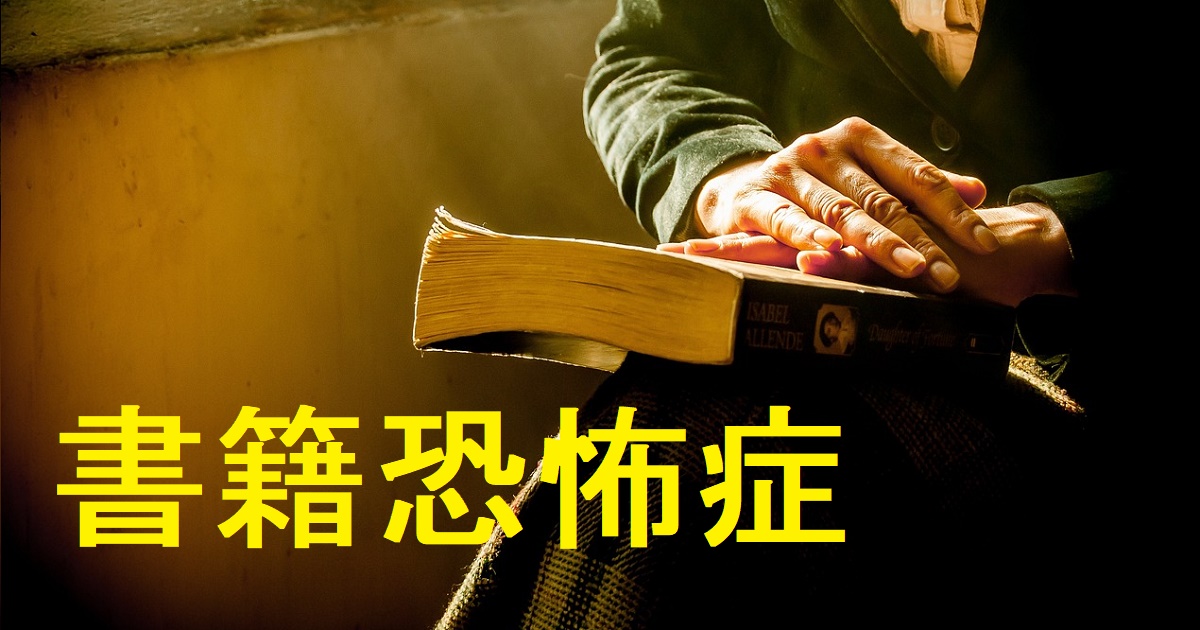

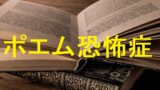

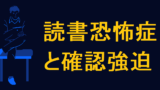
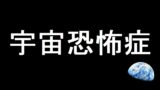


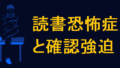
コメント